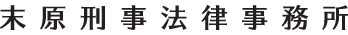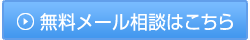誰かの供述が信用できるかどうかを判断する際,裁判では一定の手法が用いられます。
例えば,XがAという供述をしているが,これは客観的証拠と整合しており,一貫しており,迫真的であり,この点について嘘をつく理由もなく…,などといった思考過程を経て,Xの供述は信用できる,という結論が導かれます。
ここで注意しなければならないのは,Aという供述に限り信用できるという話ではなく,Xという人間は信用できる,という属人的な判断が行われていることです。
そして,一度Xは信用できるという話になると,XのBという供述も,Cという供述も,…すべて信用できる,となり,そのまま事実認定に用いられることになります。
ですが,およそ人間というものは,真実を述べることもあれば,虚偽を述べることもあり,Yはまったくの正直者,Zはまったくの嘘つき,というように,画然と分けられるものではないように思います。
XのBやCといった供述が信用できるかどうかは,Aと同様個別に判定されるべきであって,「信用できるX」を介して供述間を自在に移動するようなことをしていては,誤った事実認定が行われる危険性があるように思われます。
裁判官には,ごく真っ当な感覚に従った,常識的な事実認定をしてもらいたいと,常々願っているところです。(末原)
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京