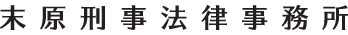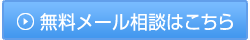横浜地裁では,裁判員裁判だけでなく,通常裁判においても,被告人供述調書の採否を留保し,被告人質問を先行させる,という運用が行われています。
一見すると,公判中心主義の徹底ということで,望ましい運用のようにも思われますが,個人的には,若干の疑問を覚えるところです。
被告人質問は,ほとんどの場合,弁護人の主質問から行われますが,被告人供述調書が未採用のため,罪体・犯情から質問していくことになります。
ですが,いくら認め事件とはいえ,罪体・犯情を立証すべきは検察官であり,それを弁護人に質問させるというのは,基本的な立証構造にそぐわない運用であるように思われます。
また,弁護人がその立場に即した主質問を行えば,網羅的にはなり得ず,結局,検察官が反対質問において網羅的に質問していくことになり,主質問を弾劾する反対質問という基本構造が崩れることが懸念されます。
ですので,罪体・犯情の主質問は検察官が,一般情状の主質問は弁護人が行うというように,認め事件の通常裁判においても,きめ細やかな運用がなされるべきではないかと思います。
否認事件であれば,主質問を行うべきは当然弁護人であるように,被告人供述の各部分を法廷に顕出したいのは弁護人なのか,検察官なのか,という基本に即した,適切な質問の振り分けが望まれます。
さらに言えば,被告人及び弁護人が,精査の上,被告人供述調書の証拠調請求に同意しているのであれば,裁判官に同じ内容を一から聞いてもらうことにさほどの意味はないように思われる上,質問時間が十分に確保されなければ,かえって立証が杜撰になる弊害をも招きかねないのではないか,という疑問も覚えるところです。
認め事件の通常裁判においても,被告人質問先行型の運用を続けていくべきか否か,基本的な立証構造などを踏まえた,慎重な検討が望まれます。(末原)
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京